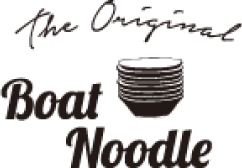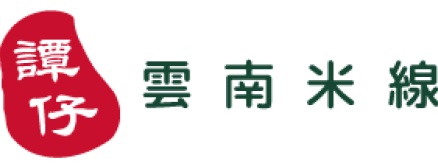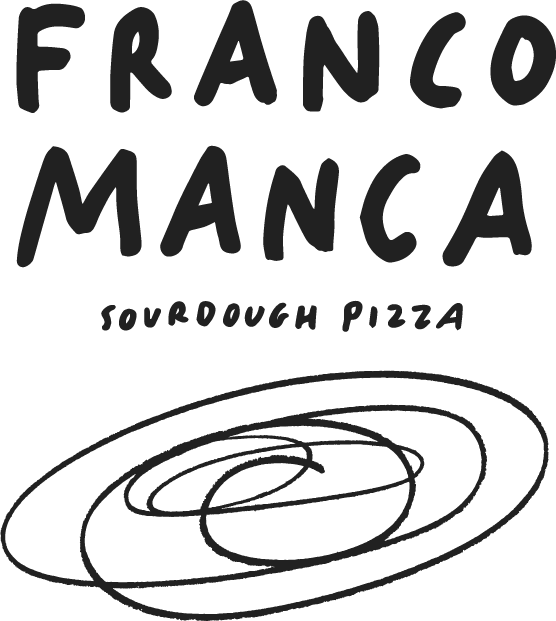◆PROFILE
三澤久雄ビクター 2022年8月入社
海外事業本部 Marugame Udon BU サブリーダー
イギリス・インペリアルカレッジ卒業(経済学・物理学専攻)
メキシコ生まれ、ベルギー育ち。これまでユニリーバ社のイギリス本社をはじめ、数々のグローバルカンパニーでマーケティングやブランディングの最前線で活躍。父親の母国である日本の食文化を代表するうどんを世界中に広めようと、現在は丸亀製麺の海外戦略部門において実質的なエグゼクティブ職として、世界を股にかけて活躍中である。
うどんを、丸亀製麺を世界中に知らしめていく。
“世界を知る男”が挑む、グローバル戦略とは。
◆chapter 1
“誰かが喜んでくれる”
マーケティングの根幹こそが自分の仕事です。
“世界を知る男”が挑む、グローバル戦略とは。
◆chapter 1
“誰かが喜んでくれる”
マーケティングの根幹こそが自分の仕事です。
・トリドールホールディングス以前のキャリアについて教えてください。
もともと誰かを喜ばせることが好きな性格でして、就職先は消費者を相手とするビジネスができる企業を探しました。いくつもの候補の中で私が選んだのは、イギリスに本社を構えるユニリーバ社。25年ほどオーストラリアや日本、フランス、タイなどの現地法人に勤務しました。当時は男性化粧品をはじめとする生活雑貨などのマーケティングに関わり、ブランディングや新製品開発などを担当しました。
ユニリーバ社を退職後はアメリカ・アトランタ州にあるニューウェル・ブランズ社やフランスのBIC社で、文房具などのマーケティングに従事していました。途中で仲間とコンサルティング会社を設立したのですが、マーケティングほどのおもしろさを感じることはなかったですね。その時に企業と相対するビジネスではなく、消費者のことを考える仕事の方が自分に合っていると思いました。

・では、なぜトリドールホールディングスへ転職されたのですか。
これには3つの理由があります。一つ目はトリドールのビジネスが「消費者向け」であること。二つ目は私が「飲食が好き」であること。これは食べることだけではなく、自分で調理することも好きで、これまでも長めの休みを取ってメキシコ料理を勉強しに行ったこともあります。そして三つ目は「日本が好き、日本に関わる仕事がしたい」という思いがあったから。父親が日本人なのですが、これまでの人生のほとんどを海外で過ごしていました。日本には大学に入学する前、アルバイトしながら短期で日本語を勉強しに訪れた程度。しかし、当時とても勢いのあった80年代後半のカルチャーに刺激を受け、いずれは日本の魅力を世界へ発信できたらいいなと考えていたのです。
トリドールはヘッドハンティングによる転職でしたが、実をいうと最初は断ろうと考えていました。現在もですが生活の基盤がアメリカにあり、家族のこと…特に日本との距離を考えるとちょっと難しいかなと思っていたのです。しかし、代表と面談した際に本気で事業のグローバル化を進めようとする思いに触れ、私もその考えに共鳴したことが入社動機となったのです。
◆chapter 2
“店舗で食べる”体験こそが、
ブランディングのコアなのです。
“店舗で食べる”体験こそが、
ブランディングのコアなのです。
・初めての飲食業ですが、以前のキャリアとのギャップは感じませんでしたか。
これまでの物販ビジネスは消費者が喜ぶ商品を企業がつくり、小売店などで購入し使用していただくことが主な目的でした。ただ、そこで得られる体験は購入した物を通じてのみ。その点、レストランなどの飲食店では、店内の雰囲気を感じながら食事をする体験がメイン。入店してメニューの中から商品を注文し、調理されたものが目の前に提供され、美味しい料理を楽しんでいただく。この一連のオペレーションこそ飲食店におけるブランディングのコアであり、物販にはないビジネスの醍醐味です。
このシチュエーションを体験するという手法は、グローバルに展開する大手テーマパークでも同じものが展開されています。アトラクションごとにそれぞれのテーマを決めて、徹底してつくり上げられた世界観の中で非日常を体験する。それらすべてがブランディングになるという点が、飲食店のブランディングとほとんど同じなのです。

・テーマパーク的なブランディングのおもしろさが、飲食店にはあると。
消費者が体験するまで数ヶ月かかる物販に比べ、飲食店では入店から注文、会計にいたるまでの短い時間ですべての結果を出さなければなりません。業態によって差はありますが、およそ1時間という短期決戦となります。だからこそ接客から調理、衛生面など細かなところまで目を行き届かせ、どうすれば店舗のブランド力が向上していけるのか、オペレーション一つひとつを考えてコントロールしていかなければなりません。私はその一連の仕事が楽しいと感じています。
もっともこの仕事に大きなやりがいを感じられるのも、かつてユニリーバ社などで担当してきたブランディングやマーケティング、商品開発などで得た経験があったから。消費者のことを考えながらあらゆる経験を一つに集約し、動かしていける醍醐味はとても楽しいと感じています。しかし、10年前や20年前だったら果たしてどうなのか。きっとこの仕事を楽しむことはできなかったと思います。いくつもの経験が一つにまとまり、つながった今だからこそできる仕事ではないかとも考えています。
◆chapter 3
“日本流”が通用しない海外が相手。
だからリスクを恐れないチームをつくります。
“日本流”が通用しない海外が相手。
だからリスクを恐れないチームをつくります。
・三澤さんは現在、どのようなミッションをお持ちでしょうか。
今のユニットでは、2028年までに1000店舗、海外に出店するという目標があります。私はユニットの責任者としてチームを編成し、出店先の国や地域を決定しながらフランチャイズを展開するためのサポートやパッケージをつくるなどの業務を行っています。
それと同時にすでに出店している国や地域においては、今まで以上にパフォーマンスを上げていくことも大事なミッションです。実はこれまで海外展開において、現地フランチャイズへのコントロールが効かなかったケースもありました。その要因として挙げられるのは、その国や地域に対し、十分なサポートやパッケージが用意できなかったからと捉えています。本当に1000店舗を達成したいのであれば、これまでのやり方を変えていかなければなりません。
・具体的には、どのような施策を行おうとしているのでしょうか。
これは大きな課題と捉えているのですが、店舗でうどんをつくってお客様へ提供する日本流のやり方は、海外では通用しないケースも多々あります。たとえば包丁一つとっても、日本ではお手伝いや学校の授業などで子どもの頃から触る機会があります。ところがイギリスだと危険なものとして、子どもには一切触らせません。大人になってから初めて触るケースがほとんどなので、日本の感覚で調理を任せようにもうまくハマらないことも多々あるのです。
このようなギャップを埋めて課題を解決し、パフォーマンスを上げていくためには、それぞれの国や地域の文化や風習を考慮した仕組みを考え、対応させていかなければなりません。それを推し進めていく私たちのグローバルチームも、強いチームを形成して仕事を進めていく必要があります。

・強いチームを形成する上で、三澤さんが取り組んでいることは何ですか。
実は私本来の性格とは異なるのですが、目標達成に向けてリーダーが「即断即決」することを重視しています。日本では失敗したくないからと、みんなの意見を聞きながら議論に議論を重ねがちですが、そんなことを続けていても物事は前に進んではくれません。結果的にその決断が間違った方を向いていたとしても、早く行動を起こせば軌道修正もすぐに行える。さらにメンバーも迷うことなく、自分のやるべきことを実行に起こすことができる。そのスピード感が必要だと考えています。
しかし、リーダーの言うことばかりに従っているだけでは、組織としての成長にはつながりません。そこで私はリスクにとらわれることなく、メンバー一人ひとりが決断することを尊重し、それをトレーニングとして実践させています。若い世代が積極的となることで、今のチームを「みんなで決める組織」にしたい。そうすることで若手の不満や不安を自らの手で解消しながら、チームとしてより強くなっていきたいと思います。
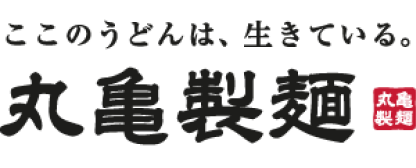

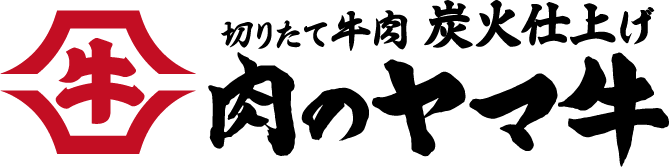
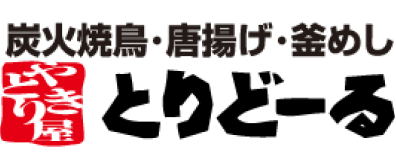
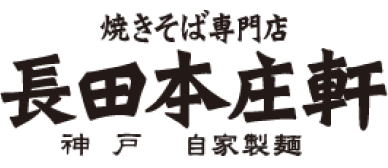

.png)

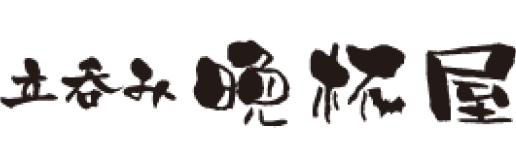
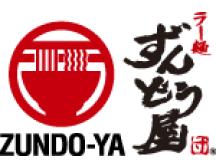
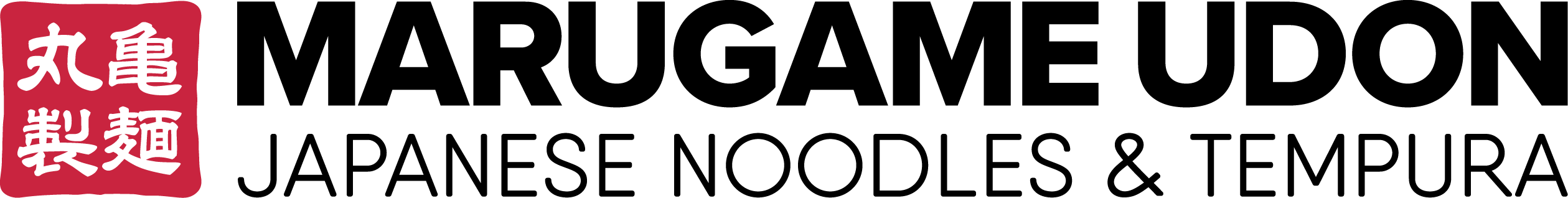
.png)