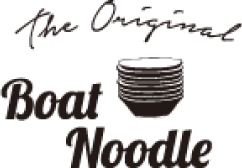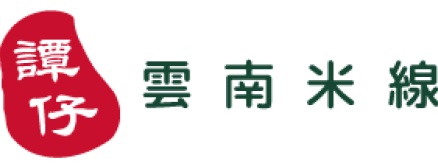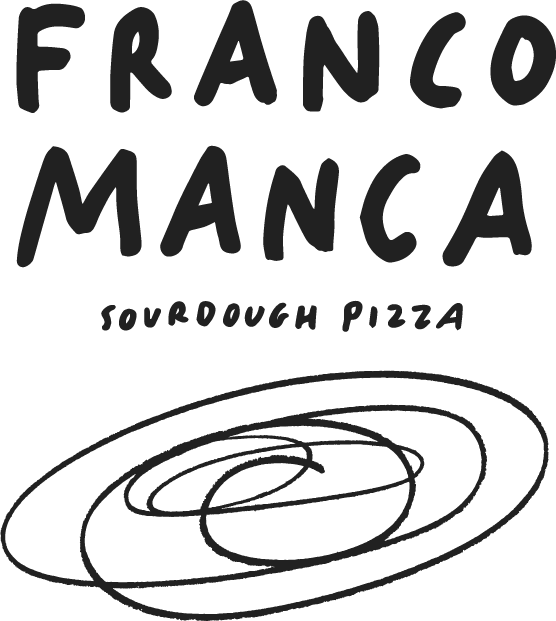员工的“幸福”
将“KANDO”扩展到世界
将“KANDO”扩展到世界
作为“全球食品公司”
进入了前进的转换期
进入了前进的转换期
不仅餐饮业,而且所有行业都受到新型冠状病毒传染病的影响,大流行已经趋同,我们Tridor集团也恢复了。在截至2024年3月的财政年度,我觉得随着日本和海外开发的20个品牌的概念得到解决,我们能够为更多客户明确提出每个品牌的概念。
“Marugame noodle”很强大,当然,“Konazu Coffee”的优点是“最近的夏威夷”的概念,我认为这是一个很好的例子,与Marugame noodle不同的新客户层诞生了。此外,2017年加入该集团的姬路猪骨拉面店“Ramen duzuya”进入成长期,国内各种商业风格都表现良好,如牛肉专卖店“肉山牛肉”繁荣的商店诞生我展示了运动。另外,在海外,2023年7月成为子公司的Fulham Shore (英国)、Tam Jai International (香港) 等也带动了增收。这一年,我觉得Marugame面条,国内其他和海外业务的每个部分都取得了平衡,我们进入了一个转折点,以推进我们的目标“全球食品公司”。
2025年3月期的中期决算,虽然丸龟制面、国内其他、海外事业等所有部门的中期销售额均达到最高水平,但由于海外事业的无利可图店铺出现减值损失等影响,预计全年将出现增收减益。
消除国内外壁垒,
员工的“幸福”致力于集团一体化
员工的“幸福”致力于集团一体化
虽然未来还会有很多曲折,但我们的海外业务的增长速度与国内业务大致相同,甚至有可能超过国内业务。鉴于此现状,东风集团有意让一直从事国内事业的员工也参与到海外事业中,努力消除国内事业与海外事业之间的隔阂,实现事业的一体化。因为我们正面临一个转折点,我们认为通过真正接触国内和国际形势来改变工人的思维方式非常重要。
虽然海外业务通常由海外事业部负责,但我们认为大家有必要以“One Toridoll”为单位共同努力。事实上,株式会社丸龟制面社长山口宏志走遍了世界各地的每一家丸龟乌冬面店,打破了地域壁垒,建立了统一的团队。通过逐步推广这些举措,我相信截至2025年3月的财年将成为员工意识转变的一年。在不久的将来,我们在海外的门店数量将超过国内门店数量,这已成为现实,我们认为有意将两者结合起来非常重要。
没有员工的幸福,“KANDO”就不会诞生
由于中餐和外卖的普及,食品配料的飙升,人力资源的短缺等,餐饮业都倾向于节省劳动力。在此背景下,通过引入食品技术等DX引起了人们的关注。我们也开始推广DX,例如将数据中心迁移到云,将后台迁移到BPO,取消VPN网络,但所有这些都需要时间和精力,并为客户提供“体验价值=令人印象深刻的体验“品尝。如果因为削减成本就谋求省人化,那就等于反而失去了我们的优势。相反,我理解这是我们不应该改变的优势。
而我们为顾客创造“感动体验”的无疑是“人”。到目前为止,“KANDO”提高了顾客的满意度,商店繁荣。我认为公司的增长来源是“KANDO”。
然而,如果没有在“KANDO”之前工作的人的“幸福=幸福”,就不会产生“KANDO”。“KANDO”和“幸福”是统一的,不是通过平衡工人的幸福和销售来选择。换句话说,它应该是“双重兼容”。
我将把我工作的商店改为“我最喜欢的地方”
在实施管理补习学校“Awata Future Juku”的同时,我为该领域的员工担任校长,“EATING MEETING”与少数总部员工分享意见和经验。如果您与他人分享“令人印象深刻的经历”,我强烈意识到提高公司利润所必需的是在那里工作的人的“感受”和“行动”。虽然它可能有点抽象,但如果工人成为朋友,赞美和帮助的“团队”,退出公司的人数会减少,商店的气氛会更好。店里的氛围好的话,客人也会聚集过来吧。作为第一步,我认为让我工作的商店成为“我最喜欢的地方”非常重要,我认为我将专注于关注工人“幸福”的尝试。
例如,创建店铺。到目前为止,我们一直在考虑商店的布局和内部,重点是如何从“客户的角度”提供令人印象深刻的体验。从现在开始,我们还将添加在那里工作的“员工观点”。作为一个具体的例子,2024年春天开业的Marugame面条东根店 (山形县) 的员工房间几乎是以前的两倍,你可以慢慢休息。虽然这是一个刚刚开始的倡议,但它非常受在东根商店工作的人的欢迎。我们将扩大我们的努力,同时验证这些商店将为商店绩效产生什么样的结果。
积极采用DX促进沟通
通过创建一个让在Tridor集团工作的员工超越距离 (地区),品牌 (业务类型) 和角色的联系,分享“幸福”和“KANDO”思想的地方,我们开发了独特的员工通信应用程序,以最大化EX (员工体验价值) 为目的。
可以在应用程序内分享在各店铺的“幸福”和对朋友的感谢。例如,如果可以通过从应用程序的帖子数量中对“幸福”和“KANDO”进行评分来分析和证明“喜欢商店并且充满活力的员工聚集的商店仍然具有很高的销售额”,则将结果传达给员工我想。随着越来越多的员工注意到这一点,它将成为其他商店蓬勃发展的催化剂,我希望强烈地成为公司的文化。
增加可持续发展领域的活动
关于可持续发展领域,问题和方向没有太大变化,但我们将“幸福”置于坐标轴的中间,并在与之进行比较的同时审查了ESG材料 (重要问题) 。我们通过食物提供“令人印象深刻的体验”,但最重要的是实现可持续发展的社会,从广义上讲,思考地球是不可或缺的。公司应该在某个地方受到社会的保护,但我觉得生意是由公司的自我建立的。
我认为不是只要自己的公司好就好,而是应该和社会、顾客等各种利益相关者一起走下去。通过这些想法和活动,我们将增加可持续发展领域的活动,以便我们能够成为许多客户想要支持的公司。
以在日本诞生的日常饮食,在世界上理所当然地被食用的未来为目标
以在日本诞生的日常饮食,在世界上理所当然地被食用的未来为目标
在日本的行业中,有许多行业不仅在日本而且在海外发展,许多公司的海外收入超过了国内收入。即使在许多如此显着增长的行业中,我认为餐饮业是一个非常大的行业,预计未来将进一步扩大。
外食产业因新冠灾难一度停滞,但预计国内市场会超过30兆日元,这样的产业并不多。它也是一个支持500万多人就业的行业,我认为这是一个需要进一步发展的行业。另一方面,很长一段时间,仅在日本就有足够的市场,出国的时机已经推迟,它也是一个“加拉帕戈斯”的行业。
我们有勇气走出国门,希望通过在海外获得比国内更高的收益,为餐饮业开辟新的道路。当然,日本料理在世界上也得到了很高的评价,但那是以一部分的高端饮食为中心的。我想在世界各地推广像乌冬面这样的日常饮食,任何人都可以熟悉。“我不知道我什么时候出生在哪个国家,但世界各地的人们都很高兴吃“乌冬面””我想与朋友一起创造这样的未来。
作为持续成长的企业,
Tridor集团将继续存在
Tridor集团将继续存在
我认为外出就餐不仅仅是提供产品,而是提供“体验”的“休闲”。除了顾客是否感到休闲外,我们还应该在日常饮食中提出“休闲”的乐趣。我想提出像乌冬面这样的“日常食物”,而不是华丽和高级的非日常饮食。
在可以轻松获得送货上门服务和便利店等各种餐点的时代,为什么要换衣服去外面吃饭?这只不过是因为外出就餐是“休闲”,如果不是“休闲”,外出就餐的意义将越来越薄。我们的目标是成为一家不断发展的公司,同时开展各种举措,创建一个即使您外出也想去吃饭的商店。我想成为一家公司,我认为增长对我们来说并不是一件特别的事情,而是一件自然的事情。
生产劳动人口的减少和少子化等,可以预想事业环境会变得更加严峻。在这种情况下,客户和员工继续聚集在Tridor集团,如果我们的目标是创建一个让员工感觉自己的位置的商店,它自然会导致为客户提供舒适的位置和服务。是的。创造这样一个地方可能需要时间,我知道这很困难,但它肯定会成为一个“以不可预测的演变开拓未来的全球食品公司”。
敬请期待我们三人组的未来。
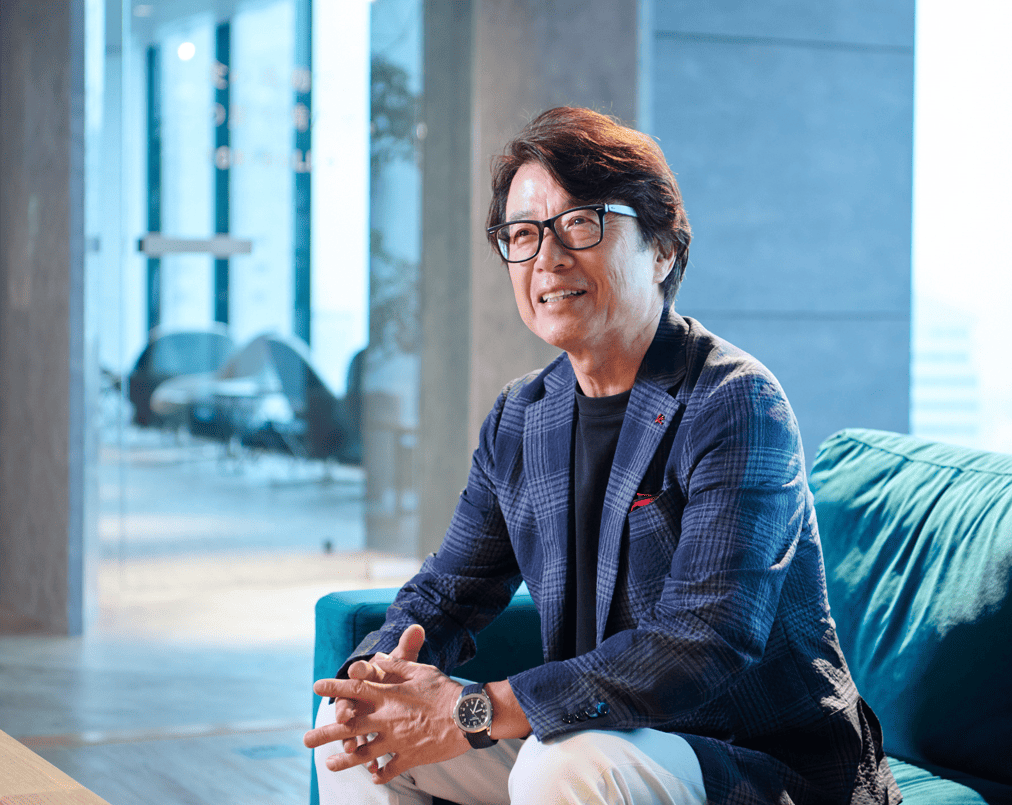
株式会社东利多控股
董事长兼首席执行官

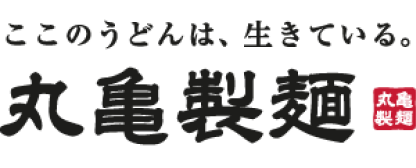

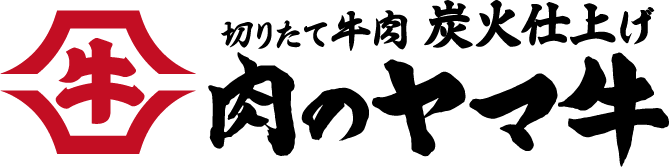
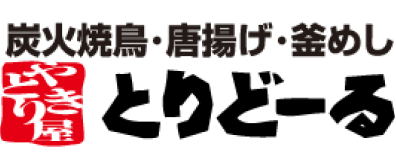
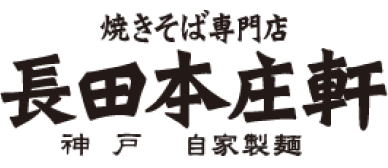

.png)

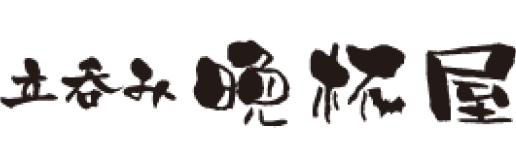
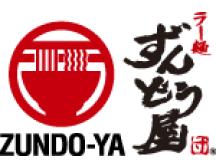
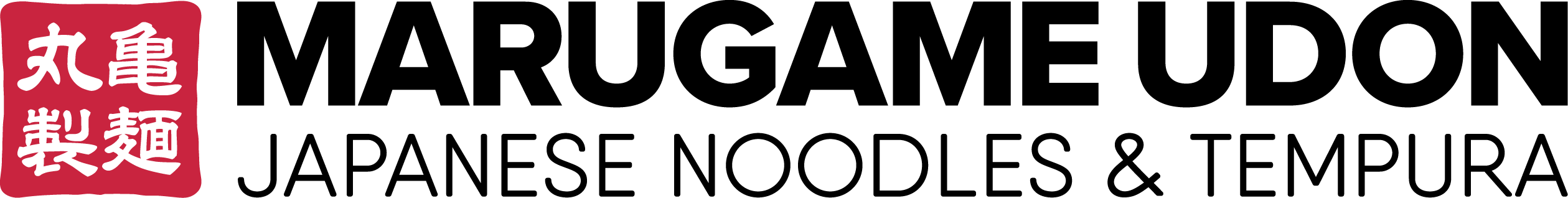
.png)